お知らせ&ブログ
那須塩原市で、大田原市で、快適な家づくりをするためのQ&A

私たちの暮す場所は寒暖差の大きな地域です。
一年を通して快適な家づくりを実現するには、寒さ対策と暑さ対策の両立が求められます。
そのためには、熱移動の原則や理論に基づいて仕様をプランニングすることが不可欠です。
そこで熱に関する質問です。
【クエスチョン1/二階建ての場合、二階が暑くなるのはなぜなのでしょうか?】

どこのハウスメーカーさんや工務店さんも、壁より天井あるいは屋根の断熱を強化しているにもかかわらずです。
このことが理論的に理解出来ているかいなかは、的確な暑さ対策を施すことが出来るかどうかということに深く関わってきます。
暑さ対策は、温暖化で暑さが厳しさを増すこれからの家づくりにとって、重要な課題と言えるでしょう。
【Q1へのA】

夏は太陽高度が高くなり、水平面(屋根面)が受ける日射量が圧倒的に多くなります。
それによって、屋根面で大量の輻射熱が発生します。
そして、上から下に移動する熱の93%を輻射熱が占めます。
しかし、断熱材は輻射熱の約9割を蓄熱し、そして放熱します。
断熱材は熱伝播遅効型熱吸収材料であり、断熱性能を上げるということは、蓄熱量を増やすことによって熱が伝わる(放熱する)までの時間を遅らせるということです。
そして、蓄熱量が増えれば、冷めるまでの時間もより長く要することとなります。
これが、壁より天井あるいは屋根の断熱を強化しているにもかかわらず、二階建ての場合、二階が暑くなる理由です。
【クエスチョン2/二階が暑いということは、平屋建てはどうなるのでしょうか?】

二階建ての二階に比べれば、一階のほうが暑さは和らぎます。
一方で、二階が乗っていない一階はどうなるのでしょうか。
二階建ての二階部分が一階に下りてくるようなものではないでしょうか。
つまり、家全体が暑くなるということです。
平屋建てなら尚更のこと、暑さ対策が重要と言えるでしょう。
【Q2へのA】

二階建ての二階が暑いのは、屋根の直ぐ下の空間であり、夏に屋根面で大量に発生する輻射熱の影響を大きく受けるからです。
平屋建ては、家全体が屋根の直ぐ下の空間となります。
ということは、平屋建ては家全体が暑くなるということです。
二階建てであれば、一階という避暑的な空間が存在しますが、平屋建てにはそのような空間が存在しません。
二階であれば、窓を開けて就寝することも出来るでしょうけれども、平屋(一階)は防犯上難しいでしょう。
そういったことも考えれば、平屋建ては尚更のこと暑さ対策が重要ですね。
【クエスチョン3/夏の夜、高断熱住宅の内部よりも無断熱である外のほうが涼しいのは、なぜなのでしょうか?】

暑さが厳しい夏の夜、冷房を使用しなければ、例え高断熱の家であっても屋内より外のほうが涼しいですよね。
外は無断熱といってもよい状況であるにも関わらずです。
夜間の熱中症リスクを軽減するためにも、原因をしっかり把握し、対策しましょう。
【Q3へのA】

断熱材は熱伝播遅効型熱吸収材料であり、蓄熱材です。
よって、断熱性能を上げれば蓄熱量が増えます。
そして、蓄熱量が増えれば、冷めにくくなります。
これにより、日没後でも屋内温度が下りにくいという具合です。
一方で、無断熱といってもよい屋外は、日没後は太陽から降り注ぐ赤外線による輻射熱の影響を受けなくなるので、気温が下がります。
したがって、夏の夜に高断熱住宅の内部よりも外のほうが涼しくなることとなるのです。
【クエスチョン4/夏の夜、明け方までに気温があまり下がらないのはなぜなのでしょうか?】

私たちの暮す地域では、陽が沈んでも明け方までにあまり気温が下がらず、熱帯夜になりやすいという特長があります。
外気温が下らなければ、住宅内の熱が尚更のこと逃げにくくなります。
そのためにも、住宅内の温度上昇をなるべく軽減出来るような処置を施したいものです。
【Q4へのA】

私たちの暮す地域の夏は、高温と多湿が重なり、雲が多く発生します。
その結果、多湿と雲が放射冷却の妨げとなり、日没後、明け方までに大幅に気温が下がることは起きにくいのです。
これにより、熱帯夜という状況を招きやすくなっています。
ちなみに、乾燥して晴天の続く砂漠は放射冷却が起きやすく、明け方までに大きく気温が下がるという具合です。
【クエスチョン5/高気密高断熱は夏涼しいと言われているのに、住宅省エネ基準の8地域で部位によりU値の基準がないのはなぜなのでしょうか?】

住宅省エネ基準において、一年を通して温暖な地域では、部位によりますがU値の基準が設けられていません。
U値とは熱貫流率のことで、数値が小さければ小さいほど断熱性能が高いことを示します。
ということは、U値の基準がないということは、断熱しなくても構わないということでもあります。
ちょっと待ってください、一年を通して温暖な地域では断熱がいらないとは、どういうことなのでしょうか。
【Q5へのA】

断熱材は蓄熱材であるがために、一年を通して暑い(暖かい)地域では屋内の暑さを助長し、一日中冷房を使うこととなり、かえってエネルギー消費量が増え、省エネ性を損なことになりかねません。
一般的に高気密高断熱の家が夏涼しいといわれるのは、冷房効率が良いという意味であり、冷房が前提となります。
【クエスチョン6/太陽に近いほうが寒く、地上に近いほうが暑いのはなぜなのでしょうか?】
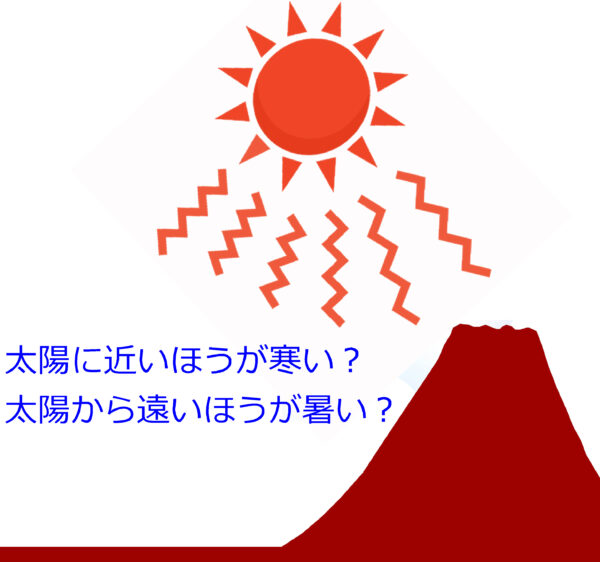
太陽から降り注ぐ赤外線は、別名「熱線」とも呼ばれます。
単純に考えれば、太陽に近いほうが暑いようにも思われますが、実際はどうでしょうか。例えば、山頂は地上よりもかなり涼しい、或いは寒いくらいですね。
この「なぜ」が解けると、暑さ対策の方向性が見えてきます。
【Q6へのA】

赤外線そのものは熱くありません。
暑さの原因は、赤外線が様々なもの(人、建物、地面、植栽等)に当ることによって発生する輻射熱です。
山頂は地平より太陽に近いですが、赤外線が当たるものが少なく、発生する輻射熱量が少ないので、気温が低くなります。
一方で、地上はあらゆる物体が太陽から降り注ぐ赤外線の影響を受け、大量の輻射熱が発生し、気温が上がるというわけです。
【クエスチョン7/気温30℃は暑いのに、湯温30℃のお風呂が寒いのはなぜなのでしょうか?】

気温が30℃まで上昇すると、かなり暑く感じられます。
35℃ともなれば、とても冷房なしでは耐えられない暑さですね。
それでも、体温よりは低い温度です。体温より低いのに暑く感じる。
一方で、湯温30℃のお風呂に入浴した場合はどうでしょうか。
夏ならともかく、冬ではとても寒くて入っていられないことでしょう。
この違いは何なのでしょうか。
【Q7へのA】

体温を36℃とすると、気温30℃は体温より低いので、暑く感じないはずです。
しかし、太陽からの赤外線が降り注ぐことで建物や道路、人体や樹木などに大量の輻射熱が生じ、暑く感じることとなります。
直射日光が当たらない木陰が涼しく感じられるのは、人体から発生する輻射熱量が軽減されるからです。
一方で、30℃の風呂に入ることで起こる熱移動は伝導であり、輻射は生じません。
そして、熱は高いほうから低いほうに移動します。
したがって、30℃の風呂に入浴した場合、体温が奪われる(体温が伝導により身体から風呂の湯に移動する)こととなり、寒く感じるのです。
【クエスチョン8/赤外線そのものは熱くないのに、冬でも太陽が当たると暖かいのは、なぜなのでしょうか?】

赤外線そのものが熱いのであれば、太陽に近いほど高温となるはずです。
しかし、実際にはその逆です。
また、冬の日差しは弱いとは言うものの、冬でも太陽が当たると暖かさを感じるものです。
赤外線自体は熱くないのに、暖かさを感じる。
この理由が解れば、その温かさを冬の寒さ対策として利用することも可能ですね。
【Q8へのA】

赤外線は熱線とも呼ばれますが、赤外線そのものは熱くありません。
しかし、冬の日差しは弱いとはいっても、赤外線が当たれば輻射熱は発生します。
だから、冬でも直射日光が当たれば暖かく感じるのです。
冬は太陽高度が低くなりますので、壁面への直達日射が増えます。
それによって発生する輻射熱を摂り込むのも、寒さ対策のひとつの方法です。
【クエスチョン9/冬の平均気温はマイナスになるほどではないのに、明け方が冷え込むのはなぜなのでしょうか?】

宇都宮の冬の平均気温は零下になるほどではありません。
しかし、夜間は冷え込み、明け方までにはかなり気温が下ります。
平均気温だけに捕らわれず、一日の気温差にも配慮した寒さ対策が望まれます。
【Q9へのA】

宇都宮の真冬の平均気温は2℃~3℃程度です。
しかし、明け方の冷え込みは厳しいものがあります。
それは、私たちの暮す地域の冬が、低温と乾燥が重なるからです。
乾燥かつ雲が少ないということは、放射冷却を妨げるものが少ないということであり、日没後の放射冷却が多く、明け方までに大きく気温が下がることとなります。
【クエスチョン10/グラスに熱いお茶を注いだ場合は結露しないのに、冷えたビールを注ぐと結露するのはなぜなのでしょうか?】
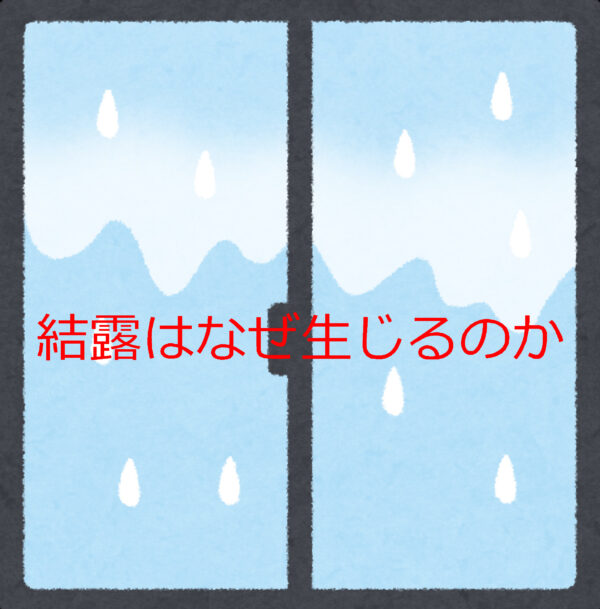
結露が生じる原因が解ると、的確な結露対策も施しやすくなります。
ちなみに、冬の湿度は高いのに、乾燥します。これは、相対湿度と絶対湿度の違いから生じるものです。
空気は温度が低いほど、維持出来る水蒸気量は少なくなります。その時その場所の気温が維持出来るMAXの水蒸気量に対して何パーセントなのかを表したものが、相対湿度です。
ですので、気温が低い場合、相対湿度は高くても、その空気に含まれる水蒸気量は少なく、乾燥するということとなります。
【Q10へのA】
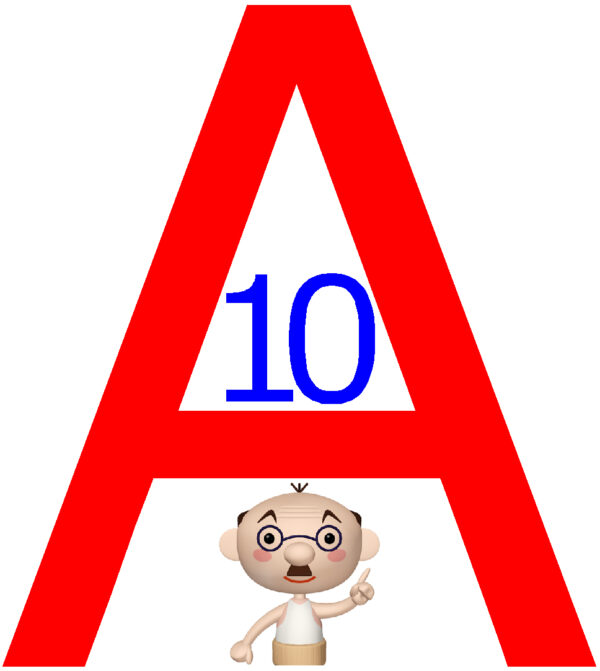
たとえば、気温30℃(室温)のときに0℃に冷やしたビールをグラスに注ぐと、温度差は30℃です。
一方で、80℃のお茶を注ぐと、温度差は50℃となります。
ということは、お茶を注いだ場合のほうが温度差は大きくなります。
結露が生じる原因のひとつは温度差ですが、それだけではありません。
湿気は暖かいほうから冷たいほうへ移動します。
だから、グラスのほうが暖かい場合は、そこに湿気が集まってこず、結露しないのです。
片や、グラスのうほうが冷たい場合は、そこに湿気が集まってきて、結露することとなります。
【クエスチョン11/暖房と冷房、停電でも可能なのはどちらでしょうか?、猛暑日に大規模停電が起きたら、どうなるのでしょうか?】
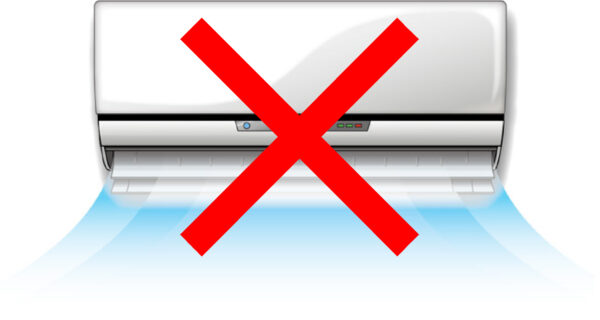
電気はなくても石油ストーブなどで暖をとることは出来ます。
また、厚着をして寒さを凌ぐということも可能でしょう。
しかし、冷房はどうでしょうか。
電気が止まってしまったら、代わるものはないといっても良いでしょう。
【Q11へのA】
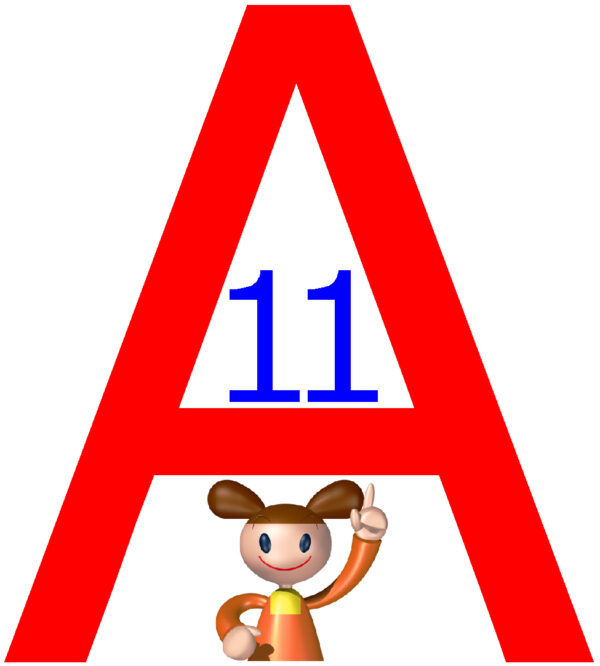
暖房は、停電時でも石油ストーブやガスストーブなどで賄うことが出来ます。
また、厚着をして寒さを凌ぐことも出来るでしょう。
しかし、冷房はエアコン以外に方法がありますか。
つまり、停電時には冷房の手段が閉ざされることとなるわけです。
もちろん、停電時は扇風機も作動しないし、薄着にも限界があります。
もし、猛暑日に大規模停電が起きたら、あたり一帯はどこも冷房が使えなくなります。
どれだけの人が、熱中症になってしまうのでしょうか。
■快適な家づくりをするための具体策
具体的にどのような家づくりをすれば、私たちの暮す寒暖差の大きな地域で、一年を通して快適な家づくりを実現出来るのでしょうか。
それは、寒さ対策と暑さ対策を両立するということでもあります。
そんなときには、冊子「これまでの家づくりは暑さを犠牲にした寒さ対策/これからの家づくりは寒さ対策と暑さ対策の両立」がお役に立ちます。
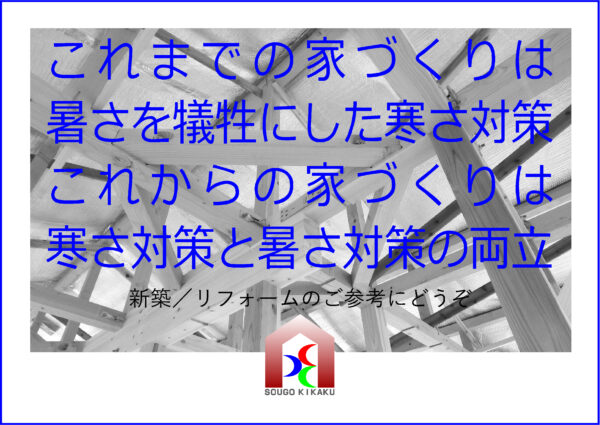
よろしければご一読下さい。無料でお送り致します。
資料のご請求、お問合せは
株式会社相互企画 山崎まで
栃木県那須塩原市南郷屋4-16-1
0287-36-3925
yamazaki@sougokikaku.co.jp
那須塩原・大田原・那須で住宅建築・不動産のことなら
相互企画にお気軽にご相談ください。
TEL 0287-36-3925(受付時間/9:00~18:00)
TEL 0287-36-3925
(受付時間/9:00~18:00)






